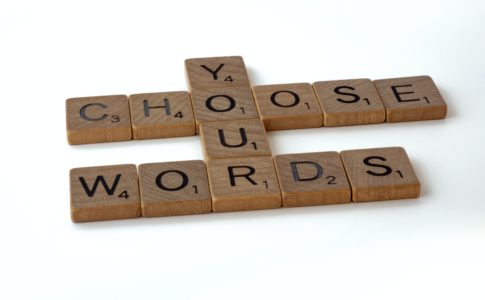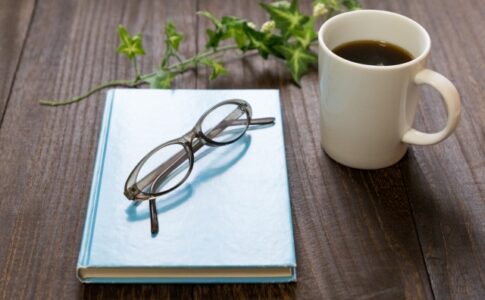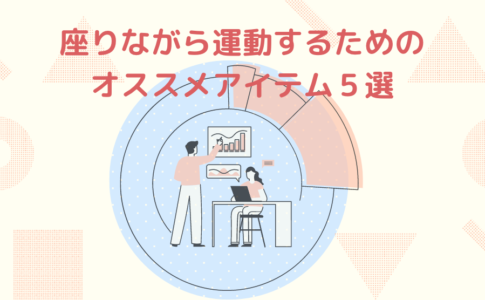どうも! ロフ です
作業療法士という職業をご存知ですか?
近年周知されつつあるものの、聞いたことがない、聞いたことがあっても具体的にどんな職業かわからない、、そのような人もまだまだ多いかもしれません。
作業療法士は、国家資格を有する専門職であり、その名のとおり作業療法を行う人です。
では作業療法とは何か?
その定義は、「作業療法は、人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。」とされています。
そう、人々の健康と幸福を促進するプロだ、ということです。
・・・何だか壮大な話になりそうですね。
しかし、作業療法は誰にとっても身近な存在なのです。
作業療法の視点をもつと、人生がもっと自分らしく豊かなものになる、私はそう信じています。
作業療法から、あなたの生活はどのような「作業」で成り立っているかを知り、健康と幸福を手に入れるためのヒントを探してみませんか?
目次
1.「作業」とは?
まず、「作業」とは何か?というお話から始めたいと思います。
作業とは、"人がしている全ての活動"のことです。
・・・ちょっと漠然としていてわかりづらいですね。
では、もう少し具体的に。
あなたは今日1日、どのような活動をして過ごしていますか?
起きて、顔を洗って、歯を磨いて、朝ごはんを食べて、着替えて、電車に乗って、仕事をして、帰宅したらお風呂に入って、夕飯を食べて、テレビをみて、寝る支度をして、眠る。
また、休日には、趣味のキャンプをしたり、友人と遊んだり、あるいは1日中ずっとベッドの上でゴロゴロしてゲームをしたり、漫画や本を読んだりする、、。
この人の日常生活に関わるひとつひとつの諸活動を、「作業」と呼んでいるのです。
つまり、あなたの毎日はたくさんの「作業」で成り立っているのです。
2.「作業」の分類
「作業」にはいくつか種類があります。
その分類の仕方は少し意見が分かれるところでもありますが、ここでは日本作業療法士協会が打ち出している分類を参考にしたいと思います。
・「セルフケア(日常的な生活行為)」
・「家事」
・「仕事」
・「余暇」
・「地域活動」
の4つです。
「セルフケア」とは、生きるために必要な活動であり、
睡眠や食事、身の回りの用事(洗顔や歯磨き、髭剃り、化粧、トイレ、入浴、着替え等)、療養が含まれます。
「家事・仕事」とは、社会的に必要な義務的活動であり、
仕事(職場の人との付き合いも含む)や学業、家事(炊事や掃除、洗濯、買い物、子どもの世話等)、通勤・通学が含まれます。
「余暇」とは、自由な時間における活動であり、
会話や交際、レジャー活動、マスメディア接触(テレビやラジオ、新聞、雑誌、マンガ、本、CD等)、休息が含まれます。
「地域活動」とは、社会参加の活動であり、
地域の行事や奉仕活動、公共の場の清掃等が含まれます。
あなたの毎日の生活がいろんな作業で成り立っていることがお分かりいただけたと思います。
自分の毎日の生活の活動をこのように細かく分類して考えてみたことはあるでしょうか?
ほとんどの人は、ないと答えると思います。
私も作業療法を学ぶまではそうでした。
ちょっと作業について知るの、楽しくなってきませんか?
あわせて読みたい!
スポンサーリンク
経験豊富なキャリアアドバイザーによる転職支援【PTOTキャリアナビ】3.作業の“意味”
さらに作業療法において重要なことは、作業の"意味"について知ることです。
例えば私たちが生きる上で欠かせない作業の一つである食事。
ある人にとっては、食事は栄養を摂取する手段として、生きるために行う活動。
ある人にとっては美味しいものを食べることは楽しみの一つであり、趣味としての活動。
ある人にとっては食事は家族団欒の場であり、社会参加としての活動。
同じ食事という活動ですが、人によってその意味は異なることがわかります。
もちろん意味は一つだけとは限らず、複数もっている場合もあります。
あなたにとって食事はどのような意味をもっているでしょうか?
作業療法士である吉川ひろみは、
「ある作業にどのような意味があるのかという問いに対して、引き起こされる感情、目的か手段か、世界とのつながり、自分らしさ、生活の構造化、健康との関連性、社会的意味、作業の類型化という8つの側面から答えることができる」
と提案してます。
「引き起こされる感情」とは、
その作業からどんな感情が起きるのか?ということです。
その作業に費やす時間が長かったとしても、何の感情の変化も起きなければその作業の意味は小さいと考えられますね。
「目的か手段か」とは、
その作業を行うことそのものに喜びや生きがい等を感じているのか?
それとも、地位や報酬を得るため等、手段として行っているのか?ということです。
例えばブログを書くという作業は、報酬がもらえるから行っている場合は手段といえますし、報酬は全くないけど趣味で行っているなら目的といえるでしょう。
「世界とのつながり」とは、
その作業をすることで、場所とつながったり、人とつながったりするのか?ということです。
前述した食事の例で、家族団欒の場としての例を挙げましたが、食事をすることで家族とのつながりが生まれていますよね。
「自分らしさ」とは、
自分がどのような存在なのかは、自分がどのような作業をするかによって決まるということです。
ある人に「私は教師です」と言われて、あなたは何かしらのイメージをもち、そこからこの人は多分こういう人なのだろうと予想すると思います。
また、その人自身も、子どもに教育をする職業に対して社会的期待に応えられるよう努力しながら、自分なりの成長を続けていくなかで、その人らしさの基盤となるアイデンティティが形成されていくことでしょう。
ある作業を通して、私はこういう人間だと感じ、他の人からもこの人はこのような人間だと感じてもらうことができるのです。
「生活の構造化」とは、
生活の中に作業が一つ入ると、生活全体がその作業に合わせて構造化するということです。仕事という作業がある日には、それにより起床時間やその前後で行うことも自然と決まってきますよね。
「健康との関連性」とは、
作業をすることで身体的、精神的、社会的に健康になったり、逆に不健康になったりするということです。
ある作業をすることでストレス発散になったり、穏やかな気持ちになったりすることもありますが、逆にストレスが溜まったりイライラしたりすることもあるでしょう。
「社会的意味」とは、
作業には時代や地域に特有の社会的意味があるということです。
今子どもから絶大なる人気を誇るYouTuberですが、10年前の日本では、企業に勤めず動画をインターネットにあげてお金を稼ぐ職業というのはあまりよく思われなかったかもしれません。
しかし、今では立派な職業として認められてきています。
このように、時間の流れとともに、作業の意味は変化するのです。
最後に、「作業の類型化」とは、
その作業が義務なのか自由なのか、公的か私的かなど、作業を類型化することによって作業の意味が決まるということです。
これは前述した、「2.作業の分類」でイメージすることができますね。
ロフ てき まとめ
このように、同じ作業でもその意味にはいろんな意味があります。
今あなたがしているその作業は、あなたにとってどのような意味をもっているでしょうか?
少し専門的な話になってしまいましたが、自分の生活がどのような作業で成り立っているか、そしてその作業が自分にとってどのような意味をもっているかを知ることで、より毎日の生活で行っていた作業をハッキリと感じることができてきたと思います。
さらに、自分と違った価値観をもつ他者を認めやすくなるかもしれません。
よりあなたらしく、豊かな人生を送るためのヒントになっていただけると幸いです。